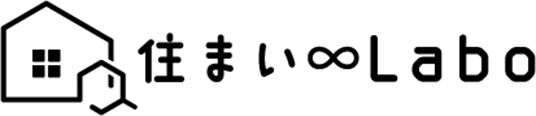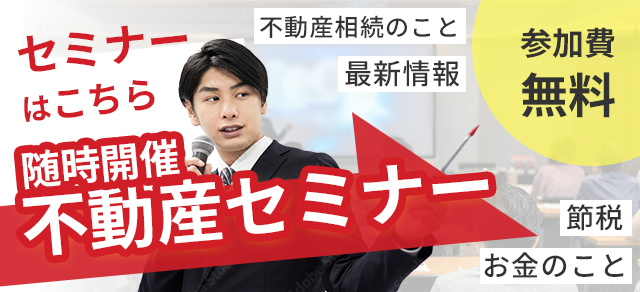相続で覚えて
おくべき基礎知識
- ホーム
- 相続で覚えておくべき基礎知識
突然の相続に備え、知っておくべき基礎知識をご紹介します
相続は突然発生することが多く、手続きや必要書類も多岐にわたるため、戸惑う方も少なくありません。そこで、相続の基本的なルールや手続きの流れ、注意点などを分かりやすくまとめてご紹介しています。急な相続にも落ち着いて対応できるよう、事前に必要な情報や知識を身につけておくことが大切です。
不動産相続で押さえるべき重要ポイント
相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要です。親族間のトラブル防止のためにも、早めの手続きを心がけましょう。
不動産相続手続きの流れ
相続人確定
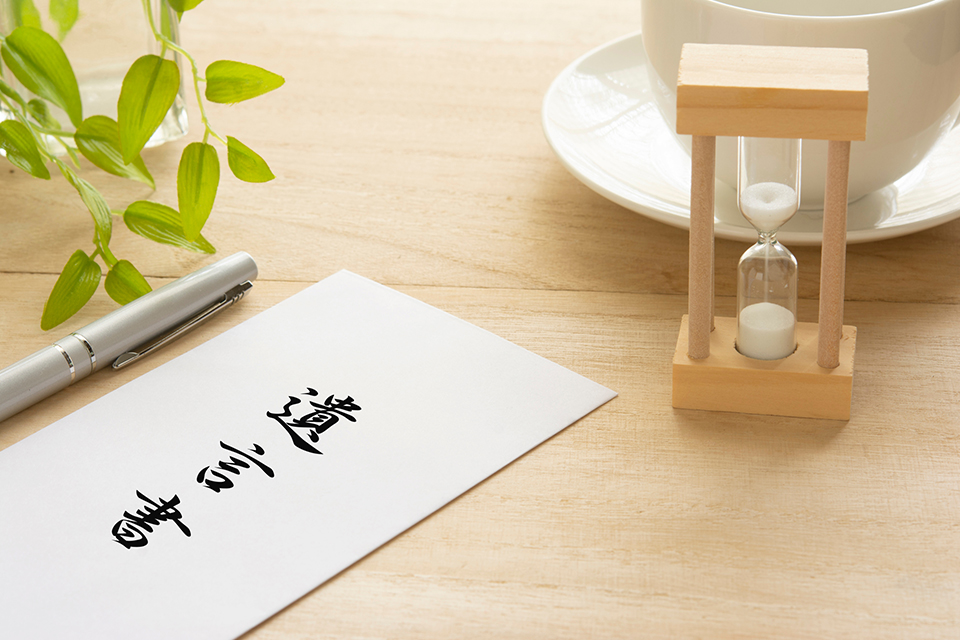
相続が発生した際は、まず遺言書の有無を確認しましょう。遺言書は自宅だけでなく、法務局や公証役場に預けられている場合もあるため、これらの場所も調べることが大切です。遺言書がない、または内容に異議がある場合は、相続人同士で遺産分割協議を行います。協議がまとまったら、相続財産の内容や全員の署名・押印を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人を確定させます。
相続登記の必要書類を準備
相続する不動産を特定するには、必要書類の準備が欠かせません。代理人が申請する場合には、委任状の提出が必要となります。
| 書類 | 入手方法 |
|---|---|
| 登記済権利証/登記識別情報 | 自宅や銀行の貸金庫など探す。 |
| 固定資産税納税通知書 | 毎年4~5月頃に市区町村から送付されます。 |
| 登記事項証明書 | 管轄法務局に請求。 |
| 名寄帳 | 市区町村役場の資産税課に請求。 |
相続登記に必要な書類は以下の通りです。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 必要な書類 | 遺産分割協議の場合 | 法定相続分による場合 | 遺言による場合 | 取得場所 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言書/遺言書情報証明書 | ◯ | 自宅、法務局、公証役場 | ||
| 遺産分割協議書 | ◯ | 関係者間で作成 | ||
| 亡くなった方の戸籍・除籍謄本 (出生から死亡まで)及び戸籍事項証明書 |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 亡くなった方の戸籍謄本 (死亡に関する事項を含む) |
◯ | 本籍地の市区町村役場 | ||
| 亡くなった方の住民票の 除票または戸籍の附票 |
◯ | ◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | ◯ | 本籍地の市区町村役場 | |
| 取得する人の戸籍謄本 (戸籍事項証明書) |
◯ | 本籍地の市区町村役場 | ||
| 相続人全員の印鑑証明書 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 相続人全員の住民票 | ◯ | 住所地の市区町村役場 | ||
| 取得する人の住民票 | ◯ | ◯ | 住所地の市区町村役場 | |
| 相続関係説明図 | ◯ | ◯ | 作成者 (弁護士や司法書士など) |
|
| 固定資産評価証明書 | ◯ | ◯ | ◯ | 不動産所在地の 市区町村役場 |
相続登記の
義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合は、相続の開始日や所有権を取得したことを知った日から3年以内に、名義変更の手続きを行う必要があります。正当な理由がなく期限までに相続登記を申請しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。「戸籍謄本の収集に時間がかかる」「相続人が病気で対応できない」など、やむを得ない事情がない限り、必ず期限内に手続きを進めましょう。
不動産相続に必要な費用を確認しよう
不動産を相続する際には、さまざまな費用が発生します。主なものとしては、登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)や、戸籍謄本・住民票など書類取得の費用、さらに司法書士や税理士への依頼料などが必要です。これらの費用について、詳しく確認していきましょう。
相続税
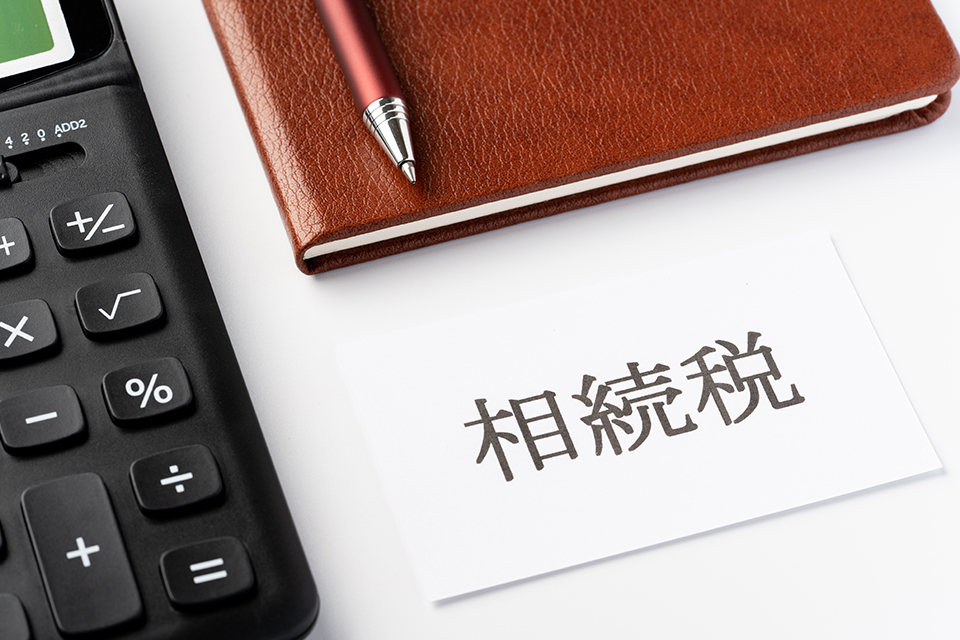
相続税は、相続した財産の時価総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算され、法定相続人が多いほど控除額も大きくなります。土地を相続した場合の時価総額は、国税庁のホームページで公開されている路線価図や評価倍率表を使って確認できます。一方、建物を相続した場合は、固定資産課税明細書や固定資産評価証明書に記載された固定資産税評価額を参考に時価総額を把握しましょう。
不動産相続における相続税の特例や控除には、さまざまなパターンがあります。それぞれ適用される条件が異なるため、ご自身の不動産がどの特例や控除に該当するか分からない場合は、不動産会社や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
| 概要 | |
|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 相続した土地について「小規模宅地等の特例」を利用すれば、一定の条件を満たすことで、最大330平方メートルまでの宅地に対し、相続税評価額を最大80%減額することができます。 |
| 配偶者の税額の軽減 | 配偶者が遺産を相続する場合、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い金額まで、相続税がかからない制度があります。この「配偶者の税額軽減」は、配偶者の経済的負担を減らすために設けられており、相続税の申告や遺産分割が確定していることなどの条件を満たす必要があります。 |
| 配偶者居住権 | 亡くなった方が所有していた建物に配偶者が引き続き住む権利(配偶者居住権)を取得した場合、この権利自体には相続税は課税されません。 |
| 相続財産と譲渡した場合の取得費加算の特例 | 相続が開始された日の翌日から3年10カ月以内に相続した土地や建物を売却すると、「取得費加算の特例」により、支払った相続税の一部を譲渡資産の取得費に加算できます。この特例を利用することで、譲渡所得税の負担を軽減することが可能です。 |
| 相続した空き家を売却した場合の特例 | 相続によって取得した家が空き家となり、それを売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けることができます。この「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」により、税負担を大きく軽減することが可能です。 |
固定資産税・都市計画税

固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に自治体から課税される税金です。これらの税金については、納税通知書と払込票が毎年4月から6月頃に送付されるため、内容をしっかり確認しましょう。
譲渡所得税
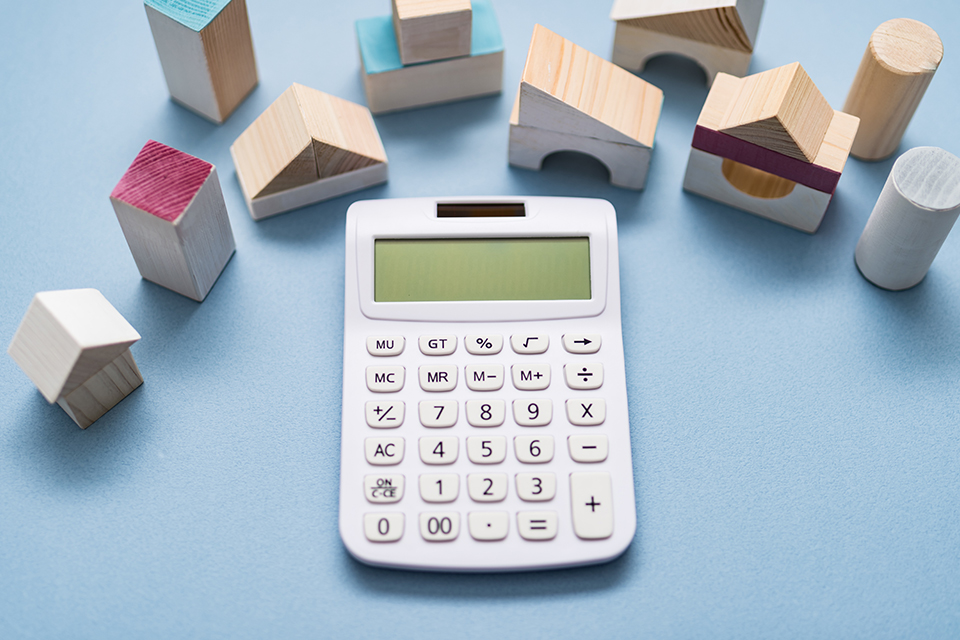
相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。これらの税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年を超える場合は「長期」、5年以下の場合は「短期」として、それぞれ税率が異なります。また、所有期間の計算には、被相続人がその不動産を所有していた期間も含まれるため、この点にも注意が必要です。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 所有期間 | 所得税(復興所得税) | 住民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以内 | 30.63% | 9% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 15.315% | 5% | 20.315% |
登録免許税
相続を理由とした不動産の所有権移転登記を申請する場合、固定資産税評価額の0.4%に相当する額の収入印紙を貼付して、登録免許税を納付する必要があります。
必要書類の入手先と取得費用
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 入手先 | 書類 | 取得費用(非課税) |
|---|---|---|
| 本籍地の市区町村役場 | 戸籍謄本 | 450円 |
| 戸籍の附票 | 450円(地域によって異なる) | |
| 除籍謄本 | 750円 | |
| 法務局 | 登記事項証明書 | 600円(不動産1件) |
| 住所地の市区町村役場 | 住民票 | 200円 |
| 住民票の除票 | 300円 | |
| 印鑑登録証明書 | 200円 | |
| 不動産所在地の都(市) 税事務所や市区町村役場 |
固定資産評価証明書 | 土地5筆まで200円 家屋5棟まで200円 |
※地域によって費用は異なります。
司法書士・税理士への依頼料
相続や登記の手続きは複雑で手間がかかるため、専門家である司法書士や税理士に依頼するのが一般的です。司法書士の報酬は3万円から10万円程度、税理士の場合は相続財産の0.5%から1%程度が相場となっています。
不動産を相続するときに注意しておくべきポイントとは
相続人が複数いる
トラブルを防ぐためには、不動産の登記を共有名義にするのは避けた方が良いでしょう。遺産分割協議では、単独名義にする現物分割や、代償分割、換価分割などの方法を検討することをおすすめします。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 分割方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 現物分割 | 複数の不動産がある場合は、それぞれの不動産ごとに相続人を割り当てる方法。 | 不公平になる場合もある。 |
| 土地を更地にして分筆登記を行う。 | 分割の仕方によっては、将来的に売却や建て替えが困難になるケースもあります。 | |
| 代償分割 | 相続人の一人が単独で不動産を所有する場合、他の相続人に対して代償金を支払い、その共有持分を買い取る形となります。 | 事業承継や、すでに相続人が居住している場合によく選ばれる方法です。ただし、代償金が高額になるケースが多く、現実的に実行が難しい場合もあります。 |
| 換価分割 | 不動産を売却して得た現金を分配する。 | 理にかなっていて公正。 |
不動産を相続したくない場合には
「老朽化した家を相続したくない」「住む予定がない」など、相続を希望しない理由がある場合は、相続放棄や相続土地国庫帰属制度の利用、売却などの方法を検討しましょう。
- 相続放棄
- プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないこと。
- 不動産売却
- 相続した不動産を売却し資金化する。
- 限定承認
- プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を相続すること。
- 寄付
- 不動産を社会福祉法人などに寄付すること。
- 国庫帰属
- 相続土地国庫帰属制度を活用して、土地を国に引き渡すこと。
なお、相続放棄や限定承認をする場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所での手続きを完了させる必要があります。
空き家になっている場合

空き家を放置すると「管理不全空家」に認定される可能性があり、その場合、自治体からの指導や勧告を受けることになります。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が適用除外となり、税額が最大で6倍に増加するケースもあります。不要な負担を避けるためにも、できるだけ早めに売却などの対応を検討しましょう。
また、相続前に空き家となっていた理由が老人ホーム入居や入院の場合、「小規模宅地等の特例」や「相続した空き家の売却に関する特例」が利用できることもあるため、事前に確認することをおすすめします。
不動産を売却する場合

不動産を売却することで得た売却益は、相続税の支払いに充てることができます。また、不動産を現金化することで、複数の相続人がいる場合でも遺産分割時のトラブルを回避しやすくなるというメリットがあります。不動産の売却方法には主に2つの選択肢があり、買主を探して売却する「仲介売却」と、不動産会社が直接買い取る「不動産買取」があります。
一般的に「仲介売却」は高値で売却できる傾向がありますが、売却が完了するまでには平均して3〜6ヶ月ほどかかることが多いです。一方で、相続税の納付期限は相続発生から10ヶ月以内と定められているため、「仲介売却」を検討する場合は、早めに不動産会社へ相談し、売却準備を進めることが重要です。
借地に建つ住宅を相続する場合

借地に建つ住宅を相続する場合、その家や借地権も相続財産となります。まずは借地契約の内容(契約期間や地代、契約の種類など)を確認し、相続人同士で遺産分割協議を行う必要があります。名義変更の際は、地主への連絡や相続登記の手続きも必要となります。また、借地権の相続は地主の承諾が不要ですが、トラブル防止のため契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。
認知症になる前に、被相続人の相続対策を進める

被相続人が認知症を発症し意思能力がないと判断された場合、その後に作成された遺言書や契約は無効となる可能性があります。このようなリスクを避けるためには、意思能力があるうちに公正証書遺言など法的に有効な遺言書を準備しておくことが重要です。また、将来に備えて任意後見制度を活用する方法も有効です。万が一、意思能力を失った場合には法定後見制度の利用など、事前に適切な対策を講じておくことが大切です。
事前に不動産価値の確認を

不動産を複数人で相続する際、「分割方法で意見が合わない」といったトラブルを防ぎ、不動産を有効活用するためには、事前に不動産の価値を把握しておくことが重要です。不動産の評価額には「地価公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」「実勢価格」など複数の種類があり、それぞれ算出方法や用途が異なります。なお、相続税を計算する際の評価額と、実際に売却する際の市場価格は一致しない場合があるため、注意が必要です。
相続が発生する前に不動産を売却しても
不動産の相場が高い場合や、小規模宅地等の特例が使えない場合、また不動産が市場のニーズと合わない場合は、相続前に売却を検討することをおすすめします。
相続に詳しい不動産会社に相談しよう

不動産会社にはそれぞれ得意分野があるため、相続に関する相談をする際は、不動産相続の実績や専門知識を持つ会社を選ぶことが大切です。このような会社であれば、税制優遇制度の活用や個別の相続対策について、適切なアドバイスを受けることができます。
住まい∞Labo(運営:株式会社Rich)は、不動産相続に豊富な実績を持つ地域密着型の企業です。お客様一人ひとりの状況に合わせて、どんなご相談にも親身に対応し、最適なサポートをご提供します。相続でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。