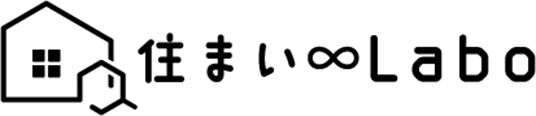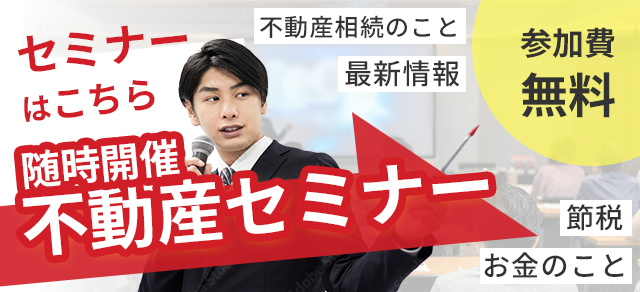被相続人に
できる対策とは?
- ホーム
- 被相続人にできる対策とは?
相続トラブルを避けるためには、
被相続人が生前に対策を講じることが重要
「相続や贈与は“そのうち考えればいい”と思っていませんか?実際には、元気なうちから準備を始めることが、相続トラブルや税金の負担を避けるための最大のポイントです。このページでは、相続や贈与を迎える前に取り組むべき準備や、基本的な税金対策についてわかりやすくご紹介します。大切なご家族を守るための第一歩として、ぜひご活用ください。
今だからこそ生前贈与を積極的に検討すべき理由

生前贈与は、「誰に、何を、どのように渡したいか」というご自身の希望を、本人の意思で具体的に実現できる大切な方法です。遺言と違い、贈与契約が成立した時点で財産の移転が完了するため、相続発生後の解釈の違いや家族間のトラブルを未然に防ぎやすいという特徴があります。
- 理由①相続税の軽減効果
- 贈与によって財産を早めに移転しておくと、その分が相続財産から除外されるため、将来の相続税の負担を軽減することができます。
- 理由②減税効果の累積
- 毎年110万円の基礎控除を活用して贈与を続けることで、長期的には大きな相続税の節税効果が期待できます。
- 理由③税制改正のリスク回避
- 将来的に制度が見直されて控除額が縮小される可能性もあるため、現行制度が適用されているうちに早めに対策を進めておくことが有利です。
- 理由④贈与時期の選択
- 不動産や資産の評価額が上昇する前に贈与を行うことで、将来の課税額の増加を防ぐことができます。
- 理由⑤希望する相手に特定財産を託す
- 生前に自分の意思を明確に伝えることで、特定の相続人や孫などに計画的に財産を移転することが可能です。たとえば、介護や家事などで特別な貢献をしてくれた家族に対し、金銭で感謝の気持ちを表すこともできます。こうした対応によって、相続時に「寄与分」の主張をめぐる争いを未然に防ぐ効果も期待できます。このように、生前贈与は単なる「節税対策」にとどまらず、ご自身やご家族にとっての安心感や納得感を得られる大きなメリットがあります。元気なうちに、ご自身の考えを反映した贈与計画を立てておくことが、将来の安心につながります。
家族が認知症と診断されたら?制度について

高齢の親が認知症と診断されると、本人の意思確認が困難になるため、不動産の売却や贈与、遺言書の作成といった法律行為ができなくなるケースが多く見られます。こうした事態を避けるためにも、早い段階で「成年後見制度」や「家族信託」の利用を検討することが重要です。
成年後見制度
判断能力が低下した本人に代わり、家庭裁判所が選任した後見人が財産管理や法律行為を行うのが成年後見制度です。この制度を利用することで本人の財産を守ることができますが、手続きが複雑であり、後見人の交代や解任が簡単ではない点も特徴です。そのため、判断能力を失う前に早めの備えを検討することが大切です。
家族信託
信頼できる家族に財産の管理や運用を託す仕組みが家族信託です。将来認知症になるリスクに備えて、親が判断能力のあるうちに契約しておけば、柔軟かつ効率的に財産を管理できるようになります。不動産の売却や贈与、収益の管理なども、家族の状況や希望に合わせて設計できるのが大きな特徴です。
生前贈与を活用して節税効果

生前贈与は、相続税の負担を抑えるための代表的な方法です。毎年110万円の非課税枠を活用し、数年に分けて贈与を行えば、相続時の財産総額を効果的に減らすことができます。また、贈与時の評価額が基準となるため、不動産など将来値上がりが予想される資産についても、早めに贈与することで課税リスクを軽減できる点がメリットです。特に、住宅取得資金や教育資金の一括贈与に関する特例制度を利用すれば、さらに大きな非課税枠を活用できます。ただし、2025年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるなど、制度の変更点にも注意が必要です。
このように、長期的な視点で早めに贈与計画を立てることで、将来の税負担や手続きの煩雑さを大きく減らすことが可能です。
生前贈与の注意点

生前贈与には多くのメリットがありますが、注意すべき点も存在します。まず、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため、超過分については税務署への申告が必要です。また、贈与契約書の作成や、振込記録などの証拠を残すことが求められる場合があり、計画的な手続きが重要となります。さらに、「相続時精算課税制度」を利用するかどうかによって、他の財産への影響や将来の相続税の課税方法が大きく変わるため、制度の特徴やデメリットも十分理解しておく必要があります。特に一度この制度を選択すると、通常の暦年贈与課税には戻せないため注意が必要です。
また、特定の相続人だけに偏った贈与をすると、後に他の相続人との間でトラブルになる可能性があるため、家族間で事前にしっかりと話し合い、情報を共有することも大切です。こうした点を踏まえ、専門家に相談しながら進めることが安心につながります。
生前贈与でよくあるご質問
- Q1.贈与税の申告は必要でしょうか?
- A1.年間110万円を超えて贈与を受けた際は、翌年の2月1日から3月15日までに申告をおこなう必要があります。
- Q2.毎年110万円以内の贈与なら課税されないのでしょうか?
- A2.原則として非課税ですが、形式的な贈与と判断されないよう贈与契約書の作成が望ましいです。
- Q3.孫に対しても贈与は可能ですか?
- A3.可能です。ただし、贈与税の非課税枠は受贈者1人につき年間110万円までです。
- Q4.住宅購入のための資金を贈与された場合、非課税になりますか?
- A4.一定の要件を満たすことで非課税となる特例があります。事前の確認が大切です。
- Q5.相続時精算課税制度とは何ですか?
- A5.贈与時の課税を先送りし、相続時にまとめて清算する制度です。適用には慎重な判断が求められます。
- Q6.生前贈与はいつ頃から始めるのが望ましいのでしょうか?
- A6.早めに始めることで、より効果的な節税が期待できます。
- Q7.贈与を受けたことを知らない相続人との間でトラブルになることはありますか?
- A7.将来的なトラブルを防ぐためにも、ご家族で情報を共有しておくことをおすすめします。
- Q8.贈与を受けた人に税金の負担はありますか?
- A8.原則として、贈与税は受け取った人が納める必要があります。
- Q9.配偶者への贈与にも税金はかかりますか?
- A9.婚姻期間が20年以上の配偶者には、2,000万円までの住宅取得に関する特例があります。
- Q10.相続時精算課税制度とは何ですか?
- A10.贈与時の課税を先送りし、相続時にまとめて清算する仕組みです。選択には慎重な判断が求められます。
長崎市・福岡市で生前贈与をお考えなら親身に寄り添う住まい∞Labo(運営:株式会社Rich)におまかせください

住まい∞Labo(運営:株式会社Rich)では、住宅業界で20年以上の経験を積んだスタッフが、ご家族それぞれの想いに寄り添いながら丁寧にサポートいたします。相続登記・贈与税の対策・家族信託まで、専門家との連携によりワンストップで対応可能。対面はもちろん、オンライン相談にも対応しており、遠方にお住まいのご家族にも安心してご利用いただけます。ご相談をいただいたからといって、無理な営業やご連絡は一切いたしません。どうぞお気軽にご相談ください。