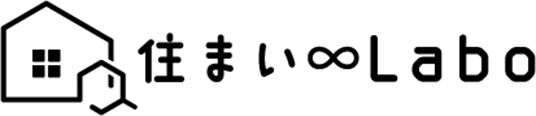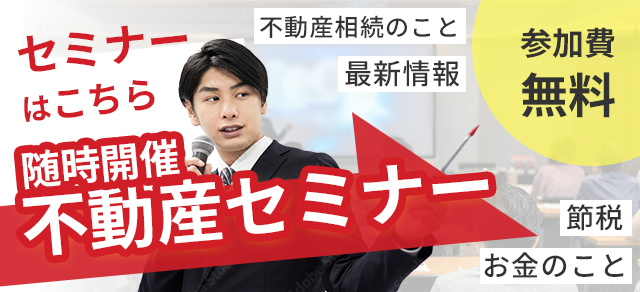相続人に
できる対策とは?
- ホーム
- 相続人にできる対策とは?
相続した不動産は放置せず、活用または売却を!
突然の相続で、空き家や空き地の管理・処分にお困りではありませんか?相続した不動産には、登記や税金などの手続きが必要で、放置すると思わぬリスクや負担を招く可能性があります。本ページでは、不動産の活用方法について、わかりやすくご案内しています。
突然の相続時に必要となる、死亡後すぐの手続きについて
ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみの中でも進めなければならない手続きが多くあります。必要な書類や費用などをまとめた専用ページをご用意しておりますので、詳細は下記よりご確認ください。
空き家(ご実家)や空き地を有効に活用するには?

相続で引き継いだ空き家や空き地を「そのまま」放置していると、管理の手間や維持費といった負担ばかりが増えてしまいます。ご家族の状況や目的に応じて、売却・賃貸・再利用など、最適な活用方法を選ぶことが大切です。このページでは、代表的な活用手段とそれぞれのメリット・デメリットについて、わかりやすく解説しています。
方法1:売却する
最もおすすめの選択肢です。固定資産税や管理の負担を減らし、現金化できる点が大きなメリットです。特に、相続税の支払いが難しい場合や活用の予定がない場合には効果的です。
- メリット
-
- 管理費や固定資産税の負担がなくなり、資産を現金化できる。
- 相続税の納付資金としても活用可能。
- 築年数が古くても、立地条件によっては売却の見込みが高い。
- 相続から3年以内なら「空き家の3,000万円特別控除」などの税制優遇が受けられる。
- デメリット
-
- 老朽化や立地によっては、相場より安くなるケースもある。
- 共有名義の不動産は、全員の同意が必要なため、手続きに時間を要することがある。
方法2:リノベーションを行い、自宅や賃貸物件として活用する
リノベーションを施して自宅として利用したり、賃貸物件として運用することで収益化が可能です。ただし、初期費用や管理の手間が発生する点には留意が必要です。
- メリット
-
- 自分や家族が住めるため、資産を無駄なく活用できる。
- リフォームの内容によっては、賃貸として安定した家賃収入も見込める。
- 老朽化によるリスクを防ぎ、地域の景観維持にも貢献できる。
- デメリット
-
- 改修費や設備投資など、初期費用が発生する。
- 賃貸に出す場合は、入居者対応やトラブル管理が必要となる。
- 需要が少ない地域では、空室のリスクも想定される。
方法3:更地にして駐車場として活用する方法
空き地を駐車場として活用すれば、安定した収入を得られる可能性があります。ただし、立地によって収益性に差が出るため、事前の調査が重要です。
- メリット
-
- 初期費用を抑えて収益化できる点が魅力。
- 車利用の多い地域では安定した需要があり、月極など柔軟な運用が可能。
- 管理の手間も少なく、トラブルが起きにくいのもメリット。
- デメリット
-
- 収益性はあまり高くなく、大きな収入は期待しにくい。
- 地面の状態によっては舗装や整備に費用がかかることもある。
- 建物を解体して更地にすると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなる場合がある。
老朽化が進んだ建物もあきらめないで!

築年数が古く、雨漏りやシロアリ被害のある物件でも、解体して更地にすることで売却の可能性が高まります。更地にすることで、建築を検討している買主にとって魅力的な土地となります。老朽化が進んだ不動産をお持ちの方も、ぜひ一度ご相談ください。
| 物件の構造 | 解体費用の目安 |
|---|---|
| 木造住宅 | 約100〜150万円 |
| 軽量鉄骨造 | 約150〜200万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 200万円~ |
※現地状況や建物構造、建物面積により変動します。くわしくはご相談ください。
相続のよくある質問
- Q1.相続税の申告はいつまでに行う必要がありますか?
- A1.相続の開始を知った翌日から10カ月以内に申告が必要です。
- Q2.相続登記をしないまま放置しても問題ないのでしょうか?
- A2.いいえ。2024年4月から相続登記は義務化されており、3年以内に手続きしない場合は過料の対象となります。すでに3年を超えている場合は、できるだけ早く当窓口へご相談ください。相続登記の手続きをしっかりサポートいたします。
- Q3.築年数が古い空き家でも売却することはできますか?
- A3.はい。古い物件でも、解体やリフォームを前提とした購入希望者が見つかることがあります。
- Q4.不動産を売却するには、どのくらいの期間がかかりますか?
- A4.早ければ1カ月以内での売却も可能です。仲介による場合は、通常3~6カ月ほどを見込んでおくとよいでしょう。
- Q5.税金の支払いが難しい場合はどうすればよいですか?
- A5.不動産を売却して納税資金を確保するのが一般的です。必要に応じて税理士と連携し、適切なご提案をいたします。
- Q6.相続した不動産に住宅ローンが残っている場合はどうなりますか?
- A6.相続では住宅ローンなどの債務も一緒に引き継がれます。ローン残債がある場合は、不動産売却代金から返済するのが一般的です。売却金額で完済できない場合には、不足分を自己資金で補うか、状況により相続放棄を検討することもあります。住宅ローンの有無は相続手続きにおいて重要な判断材料となるため、早めの確認が大切です。
- Q7.相続人が複数いる場合はどうなりますか?
- A7.相続人全員の合意による遺産分割協議書の作成が必要です。当窓口では、来店・訪問に加え、複数名でのオンライン相談にも対応しております。ご都合に合わせた方法をお選びいただけます。
- Q8.遠方に住んでいても相談することはできますか?
- A8.オンラインでのご相談にも対応しています。お忙しい方や、育児・介護などで外出が難しい方も安心してご利用いただけます。
- Q9.相続放棄をすれば、不動産の管理義務もなくなりますか?
- A9.相続を放棄しても、一定の期間は不動産の管理責任を負う場合があります。
- Q10.相談に費用はかかりますか?
- A10.いいえ、ご相談や査定はすべて無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
長崎市・福岡市で不動産相続なら
地域密着で相続手続きまで一括対応の
住まい∞Labo(運営:株式会社Rich)へご相談を

突然の相続で、不安やお困りごとはございませんか?住まい∞Labo(運営:株式会社Rich)では、相続不動産の登記から売却・税務まで、すべてをワンストップでサポートいたします。住宅業界で20年以上の実績をもつスタッフが、地域に根ざした知識とネットワークを活かして最適なご提案をいたします。対面・オンラインどちらにも対応しておりますので、空き家や空き地に関するご相談もどうぞお気軽にお寄せください。